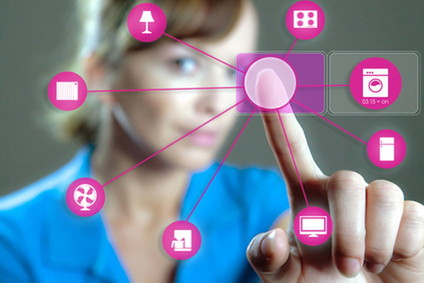
2016年10月31日
オープンソース活用研究所 所長 寺田雄一
IoTの急速な台頭でさまざまな恩恵が期待されている一方、データ量が爆発的に増大しネットワーク上で相互接続されるデバイスの数が劇的に増加したことで、IoTネットワークの開発はますます複雑化し、相互運用やセキュリティに多くの課題が見受けられる。
今回は、IoTの相互運用やセキュリティでの課題を考察する。
ネットワークのサービスプロバイダは通常、複数のサプライヤから機器を採用している。これは、各サプライヤが特定のネットワーク機能向けに提供している専用機能を利用するためだけでなく、費用対効果のためでもある。
相互運用性が実現すれば、複数のメーカーから提供されるIoT機器が相互に通信を行うことにより、統一されたユーザーエクスペリエンスを提供できるようになるだろう。機器メーカーやアプリケーション開発メーカーは、共通の参照基準(リファレンス・スタンダード)に従ってIoTネットワーク向けソリューションを構築する必要がある。
しかし現在のところ、複数の業界をまたいでIoTの発展に取り組むようなリーダー企業によるコンソーシアムは、ごくわずかしかない。
こうしたコンソーシアムの1つである「Open Interconnect Consortium(OIC)」では最近、オープンソースソフトウェアフレームワークである「IoTivity」が、IoT標準規格のリファレンス実装を発表した。この標準規格の目的は、コネクテッドデバイスやアプリケーションなどの開発メーカーを一元化することにある。
この他にもIoT関連のコンソーシアムとしては、「AllSeen Alliance」などが挙げられる。
サービスプロバイダにとって、IoT参入の障壁となり得る要素のひとつが、セキュリティである。正規ユーザーによるサービスへのアクセスを妨害する攻撃を最小限にするには、サービスプロバイダは顧客の機器、データ、ネットワークに対するアクセスコントロール対策を実施しなくてはならない。
あちこちでネットワークを使用している正規ユーザーを攻撃者から守るには、強力なデータの暗号化と認証が必要になってきている。
顧客の機器は、サービスプロバイダのネットワークへの“入り口"になることが多い。サービスプロバイダは、あらゆる機器向けにセキュリティツールや技術を導入できるようにする必要があるだろう。
http://eetimes.jp/ee/articles/1506/22/news069.html

1993年、株式会社野村総合研究所(NRI)入社。 インフラ系エンジニア、ITアーキテクトとして、証券会社基幹系システム、証券オンライントレードシステム、損保代理店システム、大手流通業基幹系システムなど、大規模システムのアーキテクチャ設計、基盤構築に従事。 2003年、NRI社内に、オープンソースの専門組織の設立を企画、10月に日本初となるオープンソース・ソリューションセンター設立。 2006年、社内ベンチャー制度にて、オープンソース・ワンストップサービス 「OpenStandia(オープンスタンディア)」事業を開始。オープンソースを活用した、企業情報ポータル、情報分析、シングルサインオン、統合ID管理、ドキュメント管理、統合業務システム(ERP)などの事業を次々と展開。 オープンソースビジネス推進協議会(OBCI),OpenAMコンソーシアムなどの業界団体も設立。同会の理事、会長や、NPO法人日本ADempiereの理事などを歴任。 2013年、NRIを退社し、株式会社オープンソース活用研究所を設立。
2022-07-28(木)15:00 - 16:00 「【サービス事業者向け】中小企業が狙われた、サプライチェーン攻撃の手口を解説 ~サイバー攻撃の被害に遭う中小企業の3つの共通点と、その対策~」 と題したウェビナーが開催されました。 皆様のご参加、誠にありがとうございました。 当日の資料は以下から無料でご覧いただけます。 ご興味のある企業さま、ぜひご覧ください。
「ERP(Enterprise Resource Planning)」とは、企業における資源(人材、資金、設備、資材、情報など)を一元的に管理し、経営を支援するための手法。その手法のために利用される業務横断型ソフトウェアパッケージは、「ERPパッケージ」「統合基幹業務システム」「統合業務パッケージ」などと呼ばれている。
「iPaaS(integration Platform as a Service)」とは「サービスとしての統合プラットフォーム」を意味し、ソリューションとして提供される。さまざまなハードウェアやミドルウェアについての煩雑な管理を大幅に軽減でき、クラウドとオンプレミスのサービスを簡単に統合して展開することが可能となる。
Analytics News ACCESS RANKING